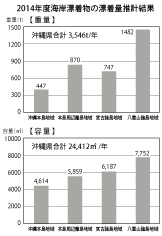■役所や企業の準備は大丈夫?
赤ちゃんからお年寄りまでの国民一人一人と企業に生涯変わらない個人番号が割り当てられる「社会保障と税の共通番号」のマイナンバー制度は、今年10月の通知開始まで実質あと半年、来年1月の運用開始まであと9カ月に迫った。
しかし内閣府の2月公表の調査では「内容まで知っていた」のは28.3%にすぎず、7割余の国民が同制度を詳しく知らないことがわかった。さらに3割余がそれぞれ個人情報の悪用や情報漏えいによるプライバシー侵害への不安、2割近くが国が膨大な個人情報を一手に握り監視することに懸念を示していることも分かった。
一方で同制度では企業も、給与支払いなどの源泉徴収票の作成などで従業員のマイナンバーが必要になり、システム整備の必要があるが、約7割がその認識に乏しく対応は鈍いという。これらはすべて八重山も同様だろう。
このように内容を知らない、あるいは制度に不安や懸念を示す住民も多い中でそのまま導入となれば役所も混乱は必至だ。制度を円滑にスタートするためにも八重山3市町は、早めに広報活動を強化し、市民や町民あるいは企業に制度を周知する必要がある。
■行政手続きが便利に
マイナンバー制度は「消えた年金」問題を背景に全国民に12桁、企業には13桁の番号を割り振って社会保障や税の情報を国が一括管理。年金や雇用保険の給付手続き、所得税の確定申告などの手続きを簡素化し、これによって書類のチェックなどに膨大な時間と人手を要する行政事務の負担を軽減し効率化しようというものだ。
具体的にはマイナンバー導入で各行政機関の情報が、専用のネット回線で共有されるため、住民票など役所への申請や届け出等の添付書類が不要になって行政手続きの利便性が向上、役所の事務作業も大幅に軽減・緩和される。
一方で県税事務所などで管理する自動車税の納付状況を市町村が確認することで高級車に乗りながら生活保護を受ける不正を摘発したり、さらに労基署の労災保険の給付内容を確認することで社会保険から一時金や年金を過不足なく受けられるようになるという。
2018年からは脱税を防ぐため、制度を預金口座にも広げる改正案が提出されたが、社会保障や税の公平・公正を図るためにも不正受給や脱税は見逃されるべきでない。
■3市町は制度の周知徹底を
10月からマイナンバーを知らせる紙製のカードが通知され、希望者には顔写真やICチップ搭載のプラスチック製の個人番号カードが交付されるという。同カードは身分証明書のほか、各種電子申請や印鑑登録証・図書館利用証など各自治体の各種行政サービスにも利用可能の予定という。
制度導入に向けては八重山3市町も既に準備に入っているが、それぞれの役所の準備状況は正直心もとない。準備が遅れれば混乱は必至であり、万全の対応が望まれる。
市民、町民、企業に制度の周知徹底を図る広報活動も新年度の4月以降に本格化するというが、情報漏えいなどの対応策は特に十分な説明が必要だ。